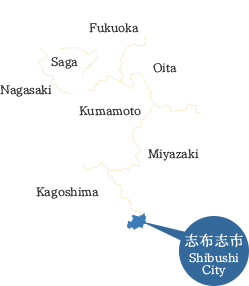本文
【国指定文化財】 志布志麓庭園
志布志麓庭園は、島津藩主が領内の約110ヵ所に武士団の集住地の一つとして設けた「志布志麓」の3つの庭園で、志布志麓を代表する武家庭園です。
これらの武家庭園は、中世志布志城の直下の谷筋に拓かれた「馬場」と呼ばれる街路沿いに帯状に展開し、近世の武家屋敷及び寺院の地割を基盤として、近代以降に手を加えられつつ継承された独特の風趣を伝える一群の住宅庭園が残されており、3庭園は独特の地形を生かして造られた志布志麓庭園の特質を表わす代表的な事例として傑出しています。
天水氏庭園

築山枯山水様式を取り入れた庭園で、江戸中期の作と伝えられていますが、作庭者は藩政時代の所有者であった村原家の祖先が築造したと伝えられています。
常緑広葉樹は遠山を象徴とし、借景に志布志城(内城)を配しているなど、景観により深く奥行きを見せています。築山の中央正面の石は、庭園意匠の中核となる 枯滝石です。枯滝石の前に脇待石・水分石・鯉魚石などの投石を配せられ、枯山水として三尊石組枯滝石組の形式をとっています。
平山氏庭園

江戸時代初期の築山鑑賞式で、作庭は古寺石峯寺時代の住職と推定されます。
大岩盤の崖を主景となし、その上に青々とした山の景観を表現し、サツキ・ツツジを配して深山幽谷の自然を風景的にまとめあげています。西隅には大日如来化身 を象徴する多宝塔をかたどった灯篭が配され、降雨の際には雨水が岩肌を伝い滝として落ちるような技巧も凝らされています。
福山氏庭園



築山枯山水様式を取り入れた庭園で、作庭者、作庭時期は不明です。
庭園は庭門を入ると、志布志麓の他の武家庭園と違って、築山の前面に広い前庭を持ち武芸の鍛錬場としても利用されていたことが伺えます。築山は主屋東側と南側にあり、海石を含む石組で縁取りされ、生垣越しに前川対岸の奈良時代創建と伝わる古刹宝満寺の甍(いらか)と背後の山並みを借景として取り入れています。
2024年7月、福山氏庭園は主屋の保存修理工事を終えて開園しました。主屋のおもて・なかえは、解体後に利用可能な部材を抽出し、再利用できない部材を新しいものと入れ替えて復元しています。庭園も修復剪定作業が行われ、古写真を基に当時の植栽を再現しています。庭園内では、戦国時代の島津氏と伊東氏の争乱に起源を持つ弓道である、四半的(一回300円)も体験できます。入園料は無料です。
志布志市の文化財マップはこちら<外部リンク>