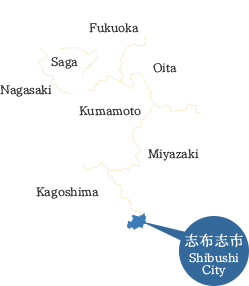本文
志布志城跡関連年表
| 年代 | 内容 |
|---|---|
| 文治5年(1189年) | 安楽平九郎為成に代わり、救仁院平八成直が救仁院地頭弁済使となる |
| 建久2年(1191年) | 救仁院平八成直、地頭弁済使職を解任される |
| 建久8年(1197年) | 建久図田帳に「島津荘寄郡救仁院90町 地頭右兵衛忠久」とある |
| 文永8年(1271年) | この頃、救仁院地頭方沙汰人は図師馬入道道西 |
| 正和5年(1316年) | 救仁院地頭沙弥蓮正、宝満寺に志布志の地を寄進 |
| 元弘元年(1331年) | 日向方惣地頭北条守時、救仁院・救仁郷の地頭代官救仁郷資清、宝満寺に土地屋敷を寄進 |
| 建武元年(1334年) | この頃、救仁郷・救仁院地方は千種忠顕の所領か? |
| 建武3年(1336年) | 重久篤兼、肝付兼重の配下が守る志布志城を攻め落とす |
| 暦応3年(1340年) | 楡井頼仲、大慈寺を創建 |
| 貞和4年(1348年) | 楡井頼仲、松尾城(白雉城)で挙兵 |
| 観応2年(1351年) | 畠山直顕、楡井頼仲の松尾城を攻め落とす 直顕、田浦条と岩広名を大慈寺に寄進 |
| 延文2年(1357年) | 楡井頼仲、挙兵するも松尾城陥落し、頼仲は自刃する 新納実久、松尾城に入る。内城の畠山直顕、実久を攻めるが、島津氏久が実久を助け、直顕は櫛間に退く |
| 延文3年(1358年) | 菊地武光、志布志に進攻し大慈寺に禁札を出す |
| 康安元年(1361年) | 島津氏久、大慈寺に岩広名半分を寄進 |
| 貞治4年(1365年) | この頃、氏久は志布志に居を定める |
| 永和3年(1377年) | 氏久、内城より出陣し、都城に今川満範を破る |
| 応永8年(1401年) | 櫛間の本田忠親、志布志城を攻め、熊田原兄弟討死(犬之馬場合戦) |
| 応永11年(1404年) | 島津元久、日向、大隅の守護職となる |
| 応永16年(1409年) | 島津元久、薩摩の守護職となる(以降、島津が三州の守護職を歴任) |
| 文明6年(1474年) | この頃、志布志に新納是久及び忠明、肝付に肝付兼忠、救仁郷に肝付主税助、櫛間に伊作久逸及び又四郎 |
| 天文4年(1535年) | 新納氏は志布志に居城し、梅北・財部・市成・垂水・牛根等を領有 |
| 天文5年(1536年) | 豊州島津氏忠朝、志布志城を攻める |
| 天文7年(1538年) | 新納氏敗れ、新納忠茂は佐土原へ去る。島津忠朝が志布志城に入る |
| 永禄元年(1558年) | 肝付兼続、肝付竹友に志布志を攻めさせ、島津方伊藤源四郎と向川原にて戦う |
| 永禄5年(1562年) | 豊州島津氏、志布志城を去り、肝付良兼が入城 |
| 永禄7年(1564年) | 肝付兼続、重臣とともに志布志城に入る 肝付竹友、地頭として志布志城に入る |
| 天正元年(1573年) | 末吉の北郷時久と肝付氏が国合原にて戦い、肝付竹友戦死 |
| 天正4年(1576年) | 志布志地頭肝付兼名、南郷で戦死 肝付兼護の所領は高山のみとなり志布志などは島津所領になる |
| 天正5年(1577年) | 志布志に島津氏の初代地頭鎌田政近が入る |
| 天正15年(1587年) | 豊臣秀吉の日向国城割により松尾城は廃城の対象に(破壊されず) |
| 元和元年(1615年) | 一国一城令発布 この頃には廃城か |
(年号は北朝のものを用いた)