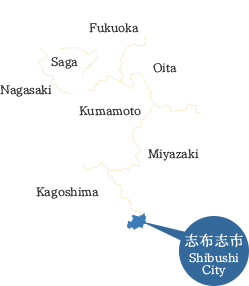本文
償却資産非課税・課税標準額の特例等について
(1)非課税となる償却資産
地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税になります。該当する償却資産を所有されている方は、償却資産申告書の「10.非課税該当資産」の有に○を付け、非課税申告書、非課税条件が確認できる資料とともにご提出ください。
なお、非課税については、目的外使用が確認された場合には、固定資産税を課税されることになりますので、ご注意ください(地方税法第348条第3項)。
使用目的が変更となり非課税適用条件を満たさなくなった場合には固定資産税(償却資産)非課税適用事由消滅申告書の提出をお願いいたします。
【非課税対象となる償却資産の例】(一部抜粋)
| 非課税対象資産 | 根拠法令 | 添付資料等 | |
| 条 | 項号 | ||
| 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 | 法第348条 | 第2項第3号 | 非課税申告書 事実を証明する書類 |
| 学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産等 | 第2項第9号 | ||
| 小規模保育事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の2 | 非課税申告書 事実を証明する書類 (施設例) 小規模保育 保育所 児童養護施設 児童発達支援センター 認定こども園 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 身体障害者福祉センター 老人デイサービス 放課後児童健全育成事業 地域子育て支援拠点事業 事業所内保育事業等 |
|
| 児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の3 | ||
| 認定こども園の用に供する固定資産 | 第2項第10号の4 | ||
| 老人福祉法に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の5 | ||
| 障害者支援施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の6 | ||
| 社会福祉事業(認定生活困窮者就労訓練事業を除く。)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の7 | ||
| 更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | ||
| 包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 | ||
| 事業所内保育事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 | ||
| 農業協同組合法等による組合等が所有し、かつ、経営する病院及び診療所並びに家畜診療所 | 第2項第11号の3 | ||
| ※適用する非課税規定に応じて事業主体、事業内容が限定されますので、所有資産のすべてが非課税となるわけではありません。 | |||
固定資産税非課税適用申告書(償却) (PDFファイル/92KB)
固定資産税(償却資産)非課税適用事由消滅申告書 (PDFファイル/66KB)
固定資産税非課税適用申告書 (エクセル) (Excelファイル/96KB)
(2)課税標準の特例が適用される償却資産
地方税法第349条の3及び同法附則第15条等の規定により、次のような資産は固定資産税が軽減されます(下表は一部抜粋)。該当する償却資産を所有されている方は、申告時に必要事項を記入のうえ、特例内容に係る資料とともにご提出ください。
【課税標準の特例対象となる償却資産の例】(一部抜粋)
| 適用条項 | 特例の対象となる資産 | 適用期間 | 特例率 | 添付資料 | ||
| 法第349条の3 | 第5項 | (1)内航船舶 | 期限なし | 2分の1 | 事実を証明する書類 | |
| 法附則第15条 | 第2項 | 第1号 | (2)公共の危害防止施設等 (水質汚濁防止) |
期限なし | 2分の1 | |
| 第2号 | (3)公共の危害防止施設等 (ごみ処理施設) |
期限なし | 2分の1 | |||
| 第3号 | (4)公共の危害防止施設等 (一般廃棄物最終処分場) |
期限なし | 3分の2 | |||
| 第4号 | (5)公共の危害防止施設等 (産業廃棄物処理施設) |
期限なし | 2分の1 3分の1 |
|||
| 第5号 | (6)公共の危害防止施設等 (下水道法による除害施設) |
期限なし | 5分の4 | |||
| 第44項(旧法附則第64条) | (7)先端設備等 (賃上げ表明なし) (賃上げ表明あり) |
3~5年間 | 2分の1 3分の1 |
|||
- (2)~(6)の設備のうち、既存の当該施設又は設備に代えて設置するもの(既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなったことに伴い、当該事業の用に供しなくなった施設等に代えて当該事業の用に供される施設等)については、対象外となります。(地方税法施行令第11条第4項)→新規設備のみが対象で、更新設備は対象外。
- (7)は中小事業者等が令和7年3月31日までに取得した一定の資産が対象となります。また、先端設備等導入計画の認定後に資産取得することが必須です。なお、適用期間及び特例率は設備の取得時期等の諸条件により異なります。